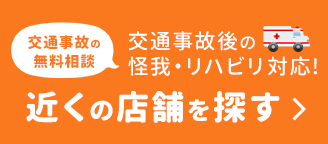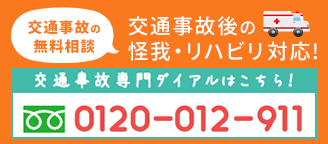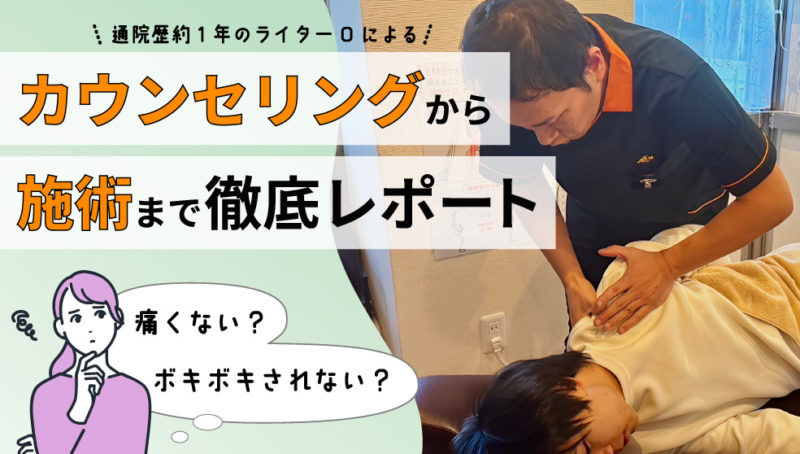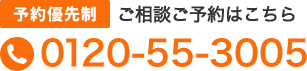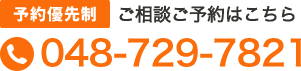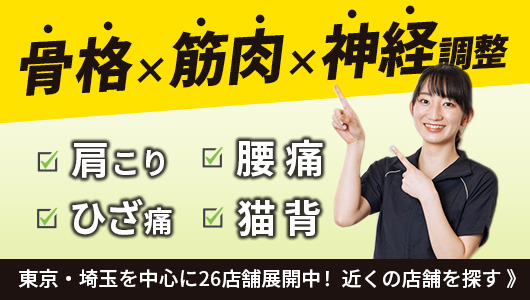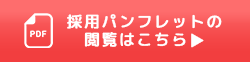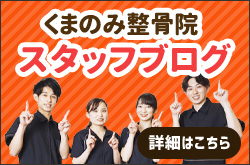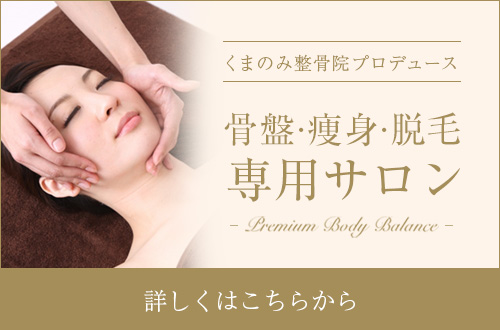鍼とマッサージとの違いとは?施術の流れや保険適用の範囲も解説

身体のつらいコリをほぐすために、鍼かマッサージを受けようと考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、どちらが自分に合っているのか見分けるのは難しいかもしれません。そこでこの記事では、鍼とマッサージの違いについて詳しく解説します。施術の流れや保険適用の範囲についてもお伝えするため、どちらが自分に合っているのかの判断材料としてお役立てください。
鍼とマッサージの違い

鍼とマッサージでは、施術内容に明確な違いがあります。それぞれ詳しく解説するため、施術を受ける際の参考にしてください。
鍼による施術内容
鍼治療は、非常に細い鍼(0.14mm〜0.34mm)を使って身体のツボを刺激する中国発祥の施術方法です。WHO(世界保険機構)でも鍼治療の効果は認められており、身体にある2,000以上のツボを刺激して自然治癒力を高める効果が期待できます。
鍼と聞くと、注射針のイメージが強いため痛みを気にされる方もいますが、髪の毛に近い太さのため刺激は抑えられています。
マッサージによる施術内容
マッサージは、手足から心臓に向かって指や手のひらで押したり、揉んだりするヨーロッパ発祥の手技療法です。全身や部分的な施術によって、身体に溜まった老廃物の排出や血行の促進作用があります。
なお、マッサージには副交感神経の活性化によるリラックス効果も期待できます。短時間でスッキリとした効果を実感できる場合もありますが、しっかりコリを改善するには、定期的な施術が必要です。
鍼とマッサージとの施術の流れの違い
鍼とマッサージでは、施術に関する流れが異なります。事前に確認しておくと、具体的なイメージが持てるため、スムーズに施術が受けられるようになるでしょう。
鍼治療の場合
鍼治療は以下の流れで施術を進めていきます。
⒈問診
⒉東洋医学的検査(脈診・腹診・舌診など)
⒊西洋医学的検査(血圧測定・聴診器での心音聴取など)
⒋鍼治療を適応するかどうかの判断
⒌施術
一度で効果を得られる場合もありますが、週に1〜3回程度継続すると、より効果を実感しやすいといわれています。症状の重さや感じ方には個人差があるため、担当者と相談しながら進めていくとよいでしょう。
なお、鍼治療を受ける際には、国家資格の「鍼灸師」が在籍している施設を選んでください。
マッサージの場合
マッサージは以下の流れで施術を進めます。
⒈カウンセリング
⒉検査
⒊施術(初回は筋肉の揉みほぐしからアプローチ)
コリの強い部分だけではなく、全身の筋肉をほぐした方が効果を長く実感できるといわれています。そのため、継続して通える場所にあるかどうかは、施設選びの重要なポイントです。
なお、施術を受ける際には、国家資格の「あん摩マッサージ指圧師」が在籍している施設を選んでください。
鍼とマッサージを併用する際の注意点

鍼治療とマッサージを併用すること自体は可能です。しかし、気をつけなければならない注意点があります。具体的には、医療機関と鍼灸院や整体院などとの保険診療の併用は認められません。
もし、医療機関で保険診療を受けている場合には、鍼灸院や整体院の施術分については自費になります。また、医療機関の受診がない場合でも、6ヶ月ごとに医師の同意書をもらわないと保険適応にはならない点もあらかじめ押さえておきましょう。
通院頻度の目安と適切な通い方
一般的には以下3つの分け方が通院頻度の目安となります。
・急性期:痛みや不快感が強く、日常生活に支障が出る場合は、週に2〜3回程度の通院が推奨されます。この期間は、症状の悪化を防ぎ早期の回復を目指すために、積極的な通院による施術が重要です。
・回復期:痛みや不快感が軽減し、日常生活に影響が少なくなった場合は、週に1〜2回程度の通院が適切です。この期間は、再発を防ぎ、身体のバランスを整えるために、定期的な通院が必要です。
・予防期:痛みや不快感がほとんどなく、日常生活に問題がない場合は、月に1〜2回程度通院が望ましいといえます。この期間は、健康維持やストレス解消のために、自分の体調に合わせて施術を受けるとよいでしょう。
なお、鍼治療とマッサージに共通していえることですが、症状の重さや感じ方には個人差があるため、通院頻度は一人ひとり異なります。
いずれの場合も、鍼とマッサージの効果を上げるためには、継続した通院が重要になります。また、セルフケアや生活習慣の改善も効果的です。
【鍼・マッサージ】保険適用の範囲と条件

鍼治療とマッサージでは、それぞれに保険適用の範囲と条件があります。ここでは、鍼とマッサージの保険適用について説明します。
鍼の場合
鍼は、以下6つの疾患に対して保険が適用されます。
・神経痛(三叉神経痛・坐骨神経痛・肋間神経痛など)
・リウマチ(関節が腫れて痛む慢性的な症状があるもの)
・頚腕症候群(上肢に現れるしびれや痛みのあるもの)
・五十肩(肩の関節が痛み腕が上がらないもの)
・腰痛症(慢性の腰痛やぎっくり腰など)
・頸椎捻挫後遺症(事故によるむち打ち症とその後遺症など)
これらの疾患に該当する場合で、医療機関での治療効果が芳しくなかったときは、医師の同意のもと保険が適用されます。その際、かかりつけのクリニックや病院の医師に同意書をもらい、鍼灸院へ提出しなければなりません。診断名や治療期間、治療方法などが記載された同意書を持って鍼灸院に行くと、自己負担額は1割〜3割になります。
また、あん摩・マッサージで同一疾病、症例で施術を受けている場合も保険は適用されません。別々の疾患、部位であれば併用可能です。
なお、部位問わず、同一月内に複数の鍼灸院の施術を受けた場合は一施設のみが保険適用となります。不明点があればかかりつけ医師や鍼灸院などに相談しましょう。
マッサージの場合
マッサージは、主に筋麻痺や関節拘縮などの運動器障害が保険適用の範囲です。これらの障害は、脳卒中や外傷などで筋肉や神経が損傷した場合に起こります。
そのほか、交通事故による障害や後遺症についても、保険適用となる場合がありますが、事故の内容や証明書などが必要です。
鍼同様、保険を適用するためには、医師の同意書が必須です。診断名や治療期間、治療方法などが記載された同意書を提出すると、自己負担額は1割〜3割になります。
まとめ
鍼とマッサージは身体のコリをほぐし、疾病によるつらい痛みを緩和する方法として、効果が期待できる施術です。施術までの流れや、保険適用にはそれぞれ条件があり、疲労改善や予防に保険は適用されませんが、積極的に利用したいところです。今一度確認してから施術を受けましょう。
鍼の施術を受けるなら、くまのみ整骨院へご相談ください。一人ひとりの身体の状態に合わせて、最適な施術を提供いたします。
おすすめ記事
東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所
- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目4−5
新宿ウエストスクエアビル 6階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院プロデュース
プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所
- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階
- 営業時間
-
平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00
日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 成増駅前院
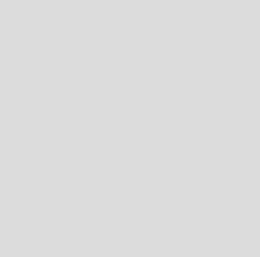
- 住所
- 〒175-0094
東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階
- 営業時間
-
平日・土日・祝:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所
- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:30/16:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所
- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00
くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階
- 営業時間
-
全日:10:00-20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所
- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 営業時間
-
平日:10:00~14:00/16:00~20:00
土曜:9:00~14:00/16:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所
- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00
くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所
- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~13:30/15:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所
- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所
- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 営業時間
-
平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30
日曜:8:30~12:30
祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |
| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |
▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所
- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所
- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所
- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 上尾院

- 住所
- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所
- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所
- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所
- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所
- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所
- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~14:00/16:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所
- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:30/14:30~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 草加院

- 住所
- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所
- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
コーポレートサイト
各院へのアクセス
東京都
埼玉県
- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階
- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階
- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階
- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28
- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階
- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階
- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階
- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階
- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階
- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階
- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階
- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階
- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階
- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階
- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階