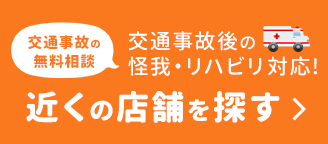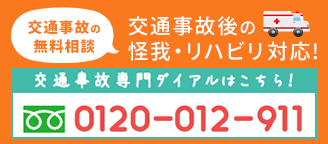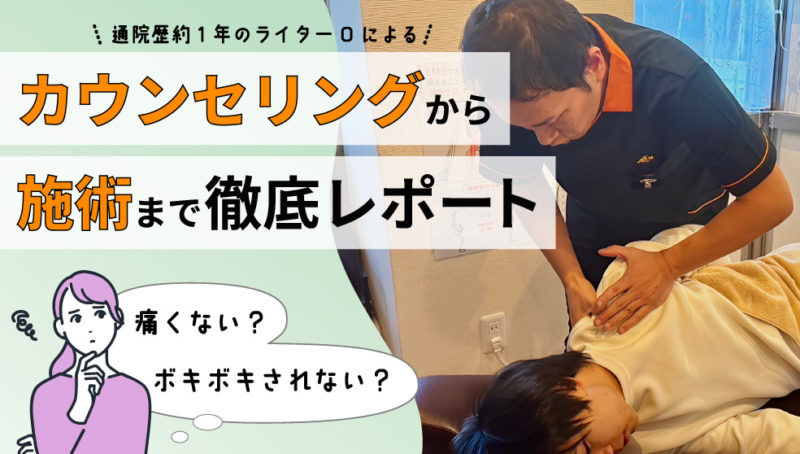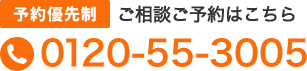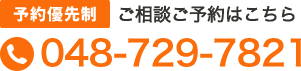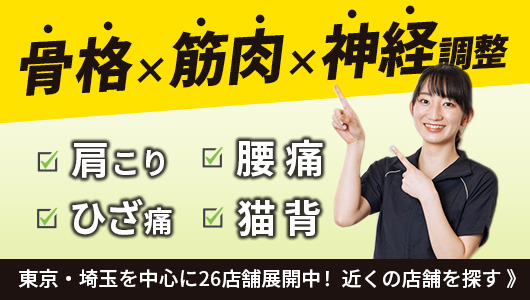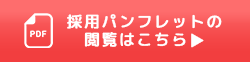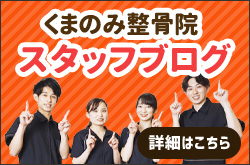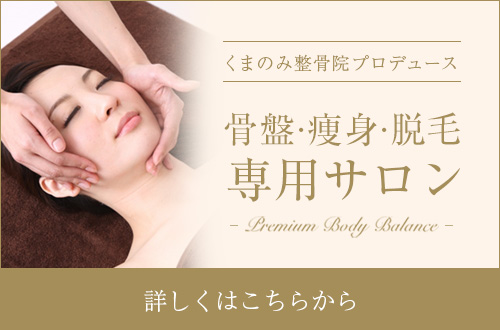片頭痛(偏頭痛)でなかなか寝られない…対処法や予防策についてご紹介

急にこめかみのあたりがズキズキと痛んだことはありませんか。夜中に片頭痛になると、痛みでなかなか寝つけないこともあります。そんなときに痛みを軽減できる方法を知りたいと考える人もいるでしょう。
今回は、片頭痛で寝られなくなったときの対処法、片頭痛が起きる原因や予防策について詳しく解説します。日常的に片頭痛で悩んでいる方は、ぜひお役立てください。
片頭痛で寝られないときの対処法

片頭痛は、脳の血管が拡張し、三叉神経が刺激されることで生じます。片頭痛の痛みで寝られないとき、我慢する必要はありません。痛みを和らげるための方法をいくつかご紹介します。
痛む箇所を冷やす
片頭痛の痛みを和らげたい場合は、まず痛む箇所を冷やしてみましょう。痛みが生じている箇所に冷たいタオルや冷却シート、氷枕を当てることで、拡張した血管が収縮されるので痛みが軽減されます。
一方、入浴して患部を温めたり、マッサージでもんだりするのは逆効果です。血管がさらに拡張し、さらに痛みが悪化するおそれがあるため、注意が必要です。
ツボを押す
東洋医学の考えでは、気と血が身体の巡りを担っていると考えます。そのため、気と血の流れ(経絡)の上にあるツボを刺激すれば、体調を整えることができるといわれています。
片頭痛の症状がある場合は、以下のツボを押してみましょう。
|
ツボの名前 |
ツボがある箇所 |
|
手三里(てさんり) |
ひじを曲げたときに出る横ジワから手首に向かって指3本分のところにある |
|
合谷(ごうこく) |
手の親指と人差し指の骨が合流する箇所からやや人差し指より |
|
足臨泣(あしりんきゅう) |
足の薬指と小指の間を足首に向かってなであげて止まる足の甲 |
|
太衝(たいしょう) |
足の親指と人差し指の間を足首に向かってなであげて止まる足の甲 |
|
崑崙(こんろん) |
くるぶしの外側とアキレス腱の間にあるくぼみ |
|
解渓(かいけい) |
内くるぶしと外くるぶしを結んだ足首全面の中央 |
ツボを押すときは、息を吐きながら5秒ほどかけて親指でゆっくり押す動きを3回繰り返します。強く押しすぎると、逆に痛みが悪化することもあるので注意してください。
鎮痛薬を服用する
痛みが強い場合は、鎮痛薬の使用をおすすめします。鎮痛薬には、市販の痛み止めとトリプタンの2種類があります。
市販の痛み止めには、ロキソニン・カロナールといった薬があり、中枢神経にはたらきかけることができます。解熱や鎮痛の効果が期待できるでしょう。
トリプタンとは、片頭痛専用の痛み止めのことです。片頭痛の痛みがあるときすぐに使うと痛みを抑えることができます。吐き気や嘔吐といった症状を抑える効果もあります。
なお、脳梗塞や心筋梗塞といった症状のある人は、トリプタンが使えません。その場合は、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)で痛みを抑えることになります。
片頭痛が起きる原因は?
 片頭痛が起きるメカニズムは完全に解明されていません。
片頭痛が起きるメカニズムは完全に解明されていません。
これまでは、脳の血管の収縮が起きた後に血管が拡張することで発生すると考えられていましたが、近年は脳そのものあるいは脳血管、三叉神経終末に原因があるといったように複数の説が提唱されています。
片頭痛が起きる主な原因としては、以下が挙げられます。
・ストレス
・寝すぎ・寝不足
・天候や気圧の変化
・空腹
・飲酒
・女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量の変化
・光、音、においといった刺激
・たばこ
・肩こり
片頭痛を引き起こす原因には、個人差があります。場合によっては、複数の原因が重なることで、片頭痛が生じるケースもあります。
片頭痛が起きないようにするための予防策
 片頭痛の痛みで苦しまないようにするには、日頃から予防しておかなければなりません。ここでは、片頭痛の予防策についてご紹介します。
片頭痛の痛みで苦しまないようにするには、日頃から予防しておかなければなりません。ここでは、片頭痛の予防策についてご紹介します。
睡眠時間に気をつける
睡眠時間の過不足によって、片頭痛が発生する原因となります。
最低でも6時間の睡眠を取るようにしましょう。8時間以上の睡眠や、週末に寝だめをした場合も片頭痛を引き起こす可能性が高くなるので、注意が必要です。
睡眠時間が短いと、疲労回復に欠かせない酸素や栄養が十分に全身に行き渡りません。そのため、疲労が溜まりやすくなり、片頭痛が引き起こされることがあります。
一方、寝過ぎの場合も、起床した際に急激に血液が流れ始めるため、三叉神経が引っ張られることで片頭痛を発症するといわれています。
睡眠時間に注意して片頭痛を避けるようにしましょう。
しっかり食事をする
片頭痛と食事には密接な関係があります。空腹の状態になると血糖値が低下して片頭痛が起きることがあるので、規則正しく3食食べて予防しましょう。
また、片頭痛を誘引する食べ物を避けることも重要です。例えば、チョコレートやチーズにはチラミンと呼ばれる物質が含まれています。チラミンには血管を収縮させる作用があり、その作用が切れると血管が拡張してしまうため、頭痛が生じることがあります。
赤ワインを始めとしたアルコールには、血管を拡張させる作用によって片頭痛を誘引する可能性があるので、飲酒は控えましょう。
片頭痛(偏頭痛)で食べたらダメな食べ物とは? 食事で気をつけたいポイント
適度な運動を取り入れる
定期的な運動は、片頭痛の予防につながります。ジョギングや早歩き、スポーツ、自転車といった軽い運動をするだけでも血行のはたらきを良くします。
また、片頭痛の予防には、腕を振る体操がおすすめです。首周りの筋肉は頭を支えており、凝り固まると頭痛の原因にもなります。
そのため、腕を振ることで頭と首を支えている筋肉(インナーマッスル)をストレッチでき、コリや疲れを取り除けます。
【手順】
1.正面を向いたまま、足を肩幅に開く
2.肘を軽く曲げ、両腕を胸の前までに水平に上げる
3.頭は動かさないよう、両肩を左右に回す
4.3の動作を2分間続ける
ポイントは、頚椎(けいつい)を軸にして、リズミカルに両肩を大きく回すことです。この運動は、椅子に座って行うこともできます。
普段運動をする習慣がない人は、この機会に片頭痛予防も兼ねて軽い運動から始めましょう。
ストレスを解消する
ストレスが原因で片頭痛が生じるケースは少なくありません。ストレスにより脳内の三叉神経が刺激されると、神経の末端から放出された炎症物質が血管を拡張させるので、痛みを生じやすくなります。
加えて、ストレスから解放された際も、副交感神経の影響により急に血管が拡張して痛みが発生することもあります。精神的・体力的に疲れているときは、ストレスを溜め込む前にゆっくり休みましょう。
趣味やスポーツといった打ち込めるものを見つければ、心身ともにリフレッシュができるので、ストレスが溜まりにくくなります。
まとめ
片頭痛で寝られないときは、痛みのある箇所を冷やしたりツボを押したりすれば軽減される可能性があります。日常的に片頭痛に悩まされている場合は、鎮痛薬も使うと良いでしょう。
片頭痛は、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れなどさまざまな原因により起こります。そのため、規則正しい生活を送るよう意識し、こまめにストレスを発散することをおすすめします。
片頭痛がなかなか治まらない場合は、肩こりや首こりが原因にあるかもしれません。もし気になる症状があれば、ぜひ「くまのみ整骨院」へご相談ください。
「くまのみ整骨院」では、一人ひとりの身体の状態を把握したうえで、適切な施術を行います。片頭痛を緩和できるよう、施術後の過ごし方や自分でできるケアもアドバイスしているため、片頭痛に悩まれている方はぜひお気軽にお問い合わせください。
東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所
- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目4−5
新宿ウエストスクエアビル 6階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院プロデュース
プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所
- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階
- 営業時間
-
平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00
日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 成増駅前院
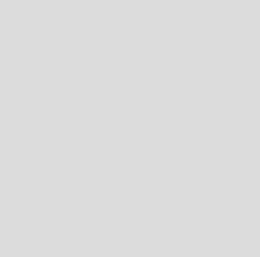
- 住所
- 〒175-0094
東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階
- 営業時間
-
平日・土日・祝:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所
- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:30/16:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所
- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00
くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階
- 営業時間
-
全日:10:00-20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所
- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 営業時間
-
平日:10:00~14:00/16:00~20:00
土曜:9:00~14:00/16:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所
- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00
くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所
- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~13:30/15:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所
- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所
- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 営業時間
-
平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30
日曜:8:30~12:30
祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |
| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |
▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所
- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所
- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所
- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 上尾院

- 住所
- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所
- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所
- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所
- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所
- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所
- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~14:00/16:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所
- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:30/14:30~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 草加院

- 住所
- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所
- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
コーポレートサイト
各院へのアクセス
東京都
埼玉県
- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階
- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階
- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階
- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28
- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階
- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階
- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階
- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階
- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階
- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階
- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階
- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階
- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階
- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階
- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階