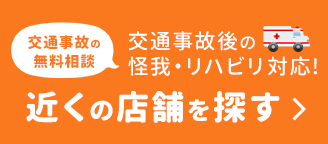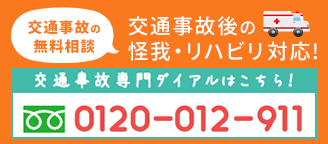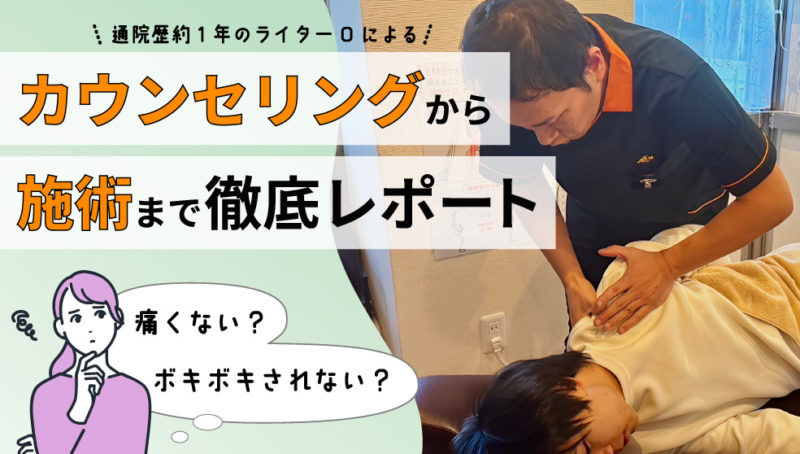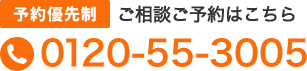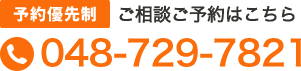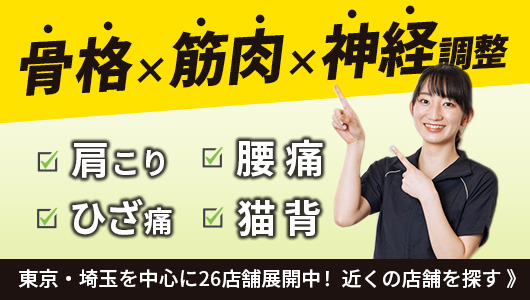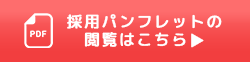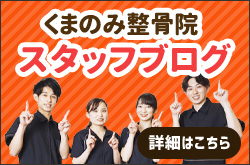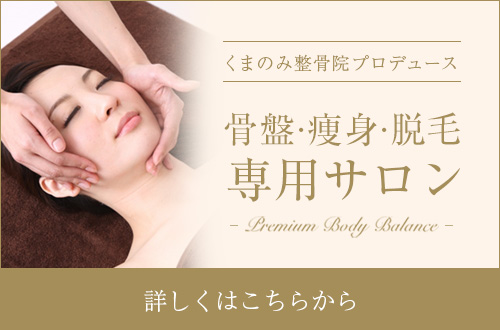なぜ首コリが起こるの?原因と痛みを和らげる方法を解説!

つらい首コリに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。首の筋肉のこわばりや痛みだけでなく、頭痛や吐き気などを引き起こす原因にもなるため、早めの対処が必要です。
今回は、首コリの原因や症状、関連する病気を紹介します。あわせて、首コリの改善策についても解説しているので、参考にしてみてください。
首コリの原因は?

首コリとは、頭部を支える首の筋肉が緊張し、違和感が生じている状態です。デスクワークが増えたうえ、日常的にスマートフォンを使用している現代人に多く見られます。
まずは、首コリの原因からみていきましょう。
1.ムチ打ちなどの外的ダメージ
首コリの原因でまずあげられるのが、外傷性の損傷です。交通事故や転倒で強い衝撃を受けたときに、頚椎(けいつい)まわりを損傷することがあります。その際のダメージが周辺の筋肉を硬化させ、痛みを引き起こします。
2.長時間のデスクワークやスマートフォンの閲覧
長時間のデスクワークやスマートフォンの操作によって、首の筋肉が硬化し、首コリになりやすい傾向があります。とくに、うつむき姿勢に注意しましょう。頭が首より前に出やすく、本来はS字にカーブする頚椎がまっすぐになる、「ストレートネック」の原因になります。
3.目の疲れ
眼精疲労も首コリが生じる原因のひとつです。パソコンやスマートフォンの長時間視聴で目が疲れると、筋肉の硬化が首の周辺にまでおよびます。その結果、首周りの血行が悪くなり、強い痛みが生じます。
4.体質の変化
40歳以降に更年期に入ると、ホルモンバランスの変化から筋肉の緊張状態が高まり、首コリになることがあります。また、加齢による頚椎の変化も首コリになりやすい一因です。頚椎の関節の骨が変形すると周囲に炎症がおき、筋肉の硬化や血行不良を引き起こします。
5.ストレス
強いストレスを受けて抑うつ状態になると、首コリになることがあります。ストレスによって自律神経の興奮が続き、全身の筋肉が緊張状態になるからです。ストレスが長期間続くと首コリが慢性化しやすく、症状が悪化しやすいので注意しましょう。
6.運動不足
運動をしない生活が続くと、筋肉が衰えます。その結果、筋肉が疲れやすくなり、肩や首のコリが生じやすくなるのです。また、運動不足によって血行が悪くなるのも、首に痛みが出やすい一因です。
7.遺伝
遺伝的に、首コリになりやすい方もいます。首コリそのものが遺伝するわけではないものの、骨格や筋肉のつき方は遺伝による影響が大きいもの。とくに、頭が大きい方、首が長い方は首まわりに負担がかかりやすいです。
首コリによって起こる症状や病気

首コリを放置すると悪化しやすく、別の病気に発展する可能性があります。首コリのおもな症状やリスクの高い病気について理解しておきましょう。
首コリの主な症状
首コリで起きる主な症状は、次のとおりです。
・首のコリ、痛み
軽度であれば違和感がある程度。慢性化すると頭痛やめまいに発展しやすい
・肩まわりのコリ、痛み
首まわりのコリが肩まで影響を与えている状態
・頭痛、めまい
首コリの筋肉の硬化が神経を圧迫して起こる
・吐き気、ドライアイ
体温調節障害や胃腸障害に発展する可能性がある
・手の痺れ
胸郭出口症候群、椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症の疑いがあるため、早期に受診が必要
首コリで見られる病気
首コリの症状が続くときは、次の病気の疑いがあります。長引く場合は身近な整形外科や内科の受診も検討してください。
・椎間板ヘルニア
背骨にある「椎間板」の一部が飛び出して神経に当たり、手足の痛みやしびれがおきる
・頚椎症性神経根症
頚椎の変成により神経根が圧迫されて、首、肩、腕などに痛みやしびれがおきる
・頸部脊椎症
頚椎内部の脊髄や神経根が圧迫されて、首、肩、手足の痛みやしびれがおきる
・変形性肩関節症
肩関節の骨や軟骨が変形し、肩や首に痛みがおきる
・五十肩
加齢により肩関節に炎症が起こり、肩、首、腕を動かすと痛みをともなう
首コリを改善する方法

ここでは、首コリを改善する方法を紹介します。首のコリがつらいときは日頃の姿勢を見直しながら、ストレッチで筋肉をほぐすと痛みがやわらぎます。痛みがひどいとき、体を動かしにくいときなどは無理をせず、病院の受診も検討しましょう。
首の横をストレッチ!
首の横にある、斜角筋をほぐすストレッチです。力の入れすぎに注意しながら、手の重みで引き伸ばしましょう。
【手順】
1.右手を左側の側頭部に添える
2.右手で頭を右側に倒し、左側の首筋を伸ばす
3.息を吸いながらゆっくりと戻し、左手に変えて反対側も引き伸ばす
首の前をストレッチ!
鎖骨から首の前にかけての筋肉をほぐすストレッチです。うつむき気味でスマートフォンを操作する癖がある方、猫背の方におすすめです。
【手順】
1.両手の親指が鎖骨にかかるようにおく
2.口を閉じて上を向き、顎を突き出すようにして首の前の筋肉を引き伸ばす
3.ゆっくり戻し、1日に2~3回を目安に行う
顎と手で引っ張るようにイメージして、首の前を伸ばしましょう。余裕があれば、首の前の筋肉を引き伸ばしているときに顎を左右にゆっくりと動かしてみてください。
首の後ろをストレッチ
頸椎に圧をかけ、首コリの動きを改善するためのストレッチです。首の痛みや疲れを感じたら、こまめに取り組みましょう。
【手順】
- 両手の指をうなじより上、首の中央から左右1cmのあたりに置く
- 両手の指を押し込んで圧をかけながら、真上を向かない程度でゆっくりと顔を上げる
- 指を上下にスライドさせて位置を変えながら、1~2の動作を3~5回繰り返す
首コリの原因を知って改善したいならくまのみ整骨院へ!
首コリのつらさを早く改善したい場合は、整骨院で施術を受けるのがおすすめです。姿勢の見直しやストレッチといったセルフケアがうまくいかないときは、1度施術を受けてみてはいかがでしょうか。
「くまのみ整骨院」では丁寧なヒアリングで、お客様の症状にあわせた施術を行っています。既往歴やライフスタイルから、お客様の首こりの原因にアプローチ。骨格を自然な状態に戻せるよう施術いたしますので、ぜひ「くまのみ整骨院」にご相談ください。
まとめ
首コリは、姿勢の悪さや目の疲れ、ストレスといったさまざまな原因で引き起こされます。たかが首コリと油断して放置していると、神経系の症状が出る可能性があるため、早めに対処しましょう。
首コリは、ストレッチによるセルフケアでも改善を目指せます。整体院の施術も活用しながら、慢性化しないように注意しましょう。
東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所
- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目4−5
新宿ウエストスクエアビル 6階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院プロデュース
プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所
- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階
- 営業時間
-
平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00
日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 成増駅前院
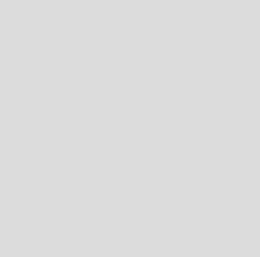
- 住所
- 〒175-0094
東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階
- 営業時間
-
平日・土日・祝:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所
- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:30/16:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所
- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00
くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階
- 営業時間
-
全日:10:00-20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所
- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 営業時間
-
平日:10:00~14:00/16:00~20:00
土曜:9:00~14:00/16:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所
- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00
くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所
- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~13:30/15:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所
- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所
- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 営業時間
-
平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30
日曜:8:30~12:30
祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |
| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |
▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所
- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所
- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所
- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 上尾院

- 住所
- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所
- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所
- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所
- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所
- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所
- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~14:00/16:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所
- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:30/14:30~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 草加院

- 住所
- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所
- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
コーポレートサイト
各院へのアクセス
東京都
埼玉県
- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階
- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階
- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階
- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28
- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階
- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階
- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階
- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階
- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階
- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階
- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階
- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階
- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階
- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階
- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階