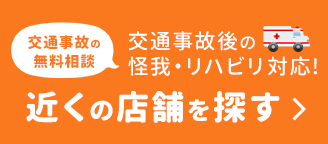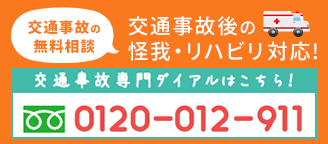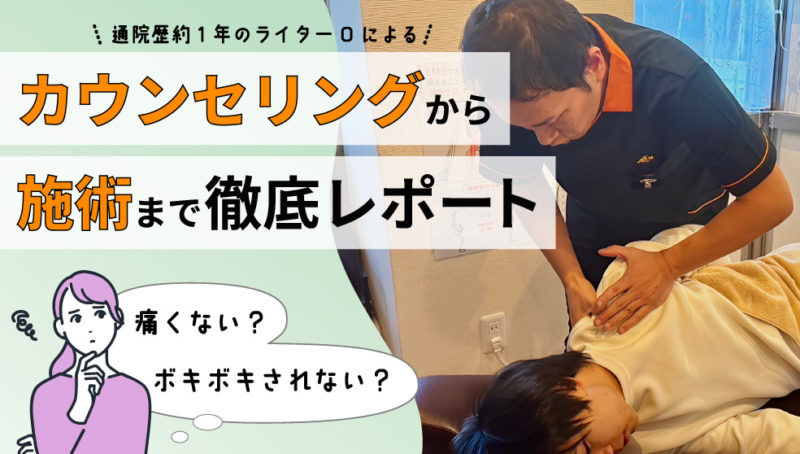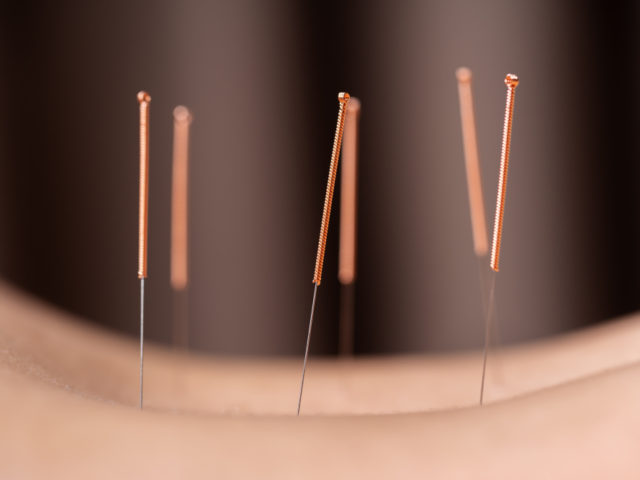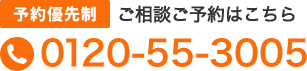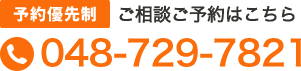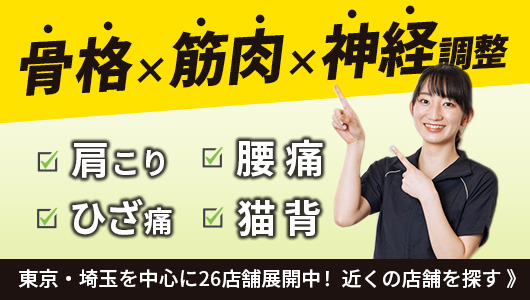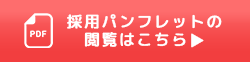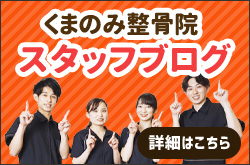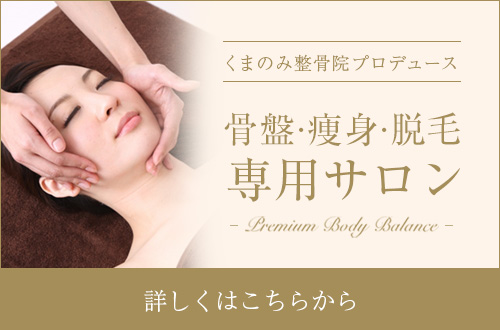スポーツ障害の治療は整骨院に行くべき?スポーツ障害でできる施術内容とは

スポーツをしていて肩や肘、すねなどにケガを負ったことがある方も多いのではないでしょうか。本記事では、スポーツ障害について解説しながら整骨院でできるスポーツ障害の治療法を紹介します。
スポーツ障害は、できるだけ早く対処することで早期改善が見込めます。また、スポーツ障害を予防したいなら、どのような部位でケガが起こるかを事前に知っておくことも大切です。
整骨院にいくべき?スポーツ障害とは

スポーツ障害とは、運動することで生じる身体の故障のことです。身体の無理な動きや過度な負担によって打撲、ねんざ、炎症、骨折などが起こります。
運動・スポーツで起こるケガは、一回の大きな衝撃によって発症するものと、身体への過度な負荷や身体の間違った使い方によって起こるものがあり、それらのケガを総称して「スポーツ障害」といいます。スポーツ障害は「使いすぎ症候群」とも呼ばれ、とくに子どもの成長期に発症することが多いです。
スポーツ障害で誤った対応をしてしまうと、骨や軟骨に変形が残ったり後遺症につながったりするおそれもあります。後遺症を残さないためにも、自分でなんとかしようとするのではなく、整骨院などで専門家による治療を受けるようにしましょう。
スポーツ障害の分類
スポーツ障害は、一回の大きな衝撃によって発症する「急性外傷」と、身体の使いすぎや間違った使い方によって起こる「慢性外傷」の二種類にわけることができます。
急性外傷
スポーツ障害の急性外傷は、スポーツ中の強い衝撃によって骨や筋肉、腱などが損傷したケガです。急性外傷は、脱臼、筋などの断裂、創傷などが該当し、次のようなシーンで起こる可能性があります。
・陸上競技中に太ももを痛めた
・ラグビー中に首や肩を強く打った
・柔道をしているときに指を痛めた
慢性外傷
スポーツ障害の慢性外傷は、スポーツを続けていく中で身体の使いすぎや間違った使い方が原因となり、骨、関節、靭帯が徐々に損傷したケガを指します。慢性外傷の発症例としては、次のようなケースがあります。
・野球を長年やっていて肩や肘が痛い
・マラソンをやっていて膝が痛い
・テニスを何年も前からやっていて肘の外側が痛い
慢性外傷は繰り返しの負荷によって起こるケガなので、受傷機転は明確ではありせん。慢性外傷を防ぐためには、運動量を調整したりフォームの見直しをしたりすることが大切です。
部位別の主なスポーツ障害

ここでは部位別に起こる主なスポーツ障害を紹介します。
首・肩
首や肩は「バーナー症候群(頸椎損傷)」、「むち打ち症(頸椎捻挫)」「野球肩」などのスポーツ障害を発症することがあります。
バーナー症候群(頸椎損傷)
バーナー症候群(頸椎損傷)は、ラグビーやアメフトなどの相手と強くぶつかり合うスポーツで、首や肩に大きな衝撃を受けた際に起こるケガです。首から肩、腕にかけて痺れや痛みが生じます。
むち打ち症(頸椎捻挫)
激しい衝突によって、首や肩の筋肉や靭帯が伸びたり断裂したりするケガを、むち打ち症(頸椎捻挫)と呼びます。首筋や肩、背中に痛みが現れることが多く、場合によってはめまいや吐き気などの症状が伴うこともあります。
野球肩
野球肩は、ボールを投げる動作をやりすぎることによって、肩関節まわりに痛みが起こるケガです。野球のピッチャーに多く見られる症状なので野球肩といいますが、テニスやバレーボール、水泳などでも生じることがあります。
肘
肘に起こりやすいスポーツ障害は、「野球肘」と「テニス肘」です。
野球肘
野球肩と同様に、ボールを投げる動作をやりすぎることによって起こるケガです。肘の内側、または外側に痛みが現れ、肘の骨や軟骨、靭帯、腱などに炎症が起こります。
テニス肘
テニス肘は肘の外側に痛みが起こるケガで、手首を伸ばす筋肉に負担がかかり続けることによって発症します。
腰
腰は、「腰椎分離症」や「腰部打撲・捻挫」などのスポーツ障害によって痛めることがあります。
腰椎分離症
腰椎分離症は、ジャンプや腰を捻る動作を繰り返すことで、腰椎の後方部分の骨に亀裂が入って起こるケガです。腰椎分離症になると、腰痛またはお尻や太ももの痛みをともないます。
腰部打撲・捻挫
スポーツ中に強い衝撃を受けたときに、腰付近の筋繊維や血管を損傷するケガを「腰部打撲」といい、運動中に腰を無理に回旋することで筋肉や靭帯を断裂するケガを「腰部捻挫」と呼びます。
膝・足
膝や足の場合は、「オスグッド・シュラッター病」や「ジャンパー膝」、「ランナー膝」、「タナ障害」などのケガを負うことがあります。
オスグッド・シュラッター病
膝の曲げ伸ばしを繰り返すことによって、膝のお皿の下部にある骨の出っ張りに痛みや腫れが生じるケガを「オスグッド・シュラッター病」といいます。成長期の子どもに起こりやすいケガです。
ジャンパー膝
ジャンパー膝は、ジャンプで膝の伸展を繰り返すことで膝付近に炎症が起こるケガです。バレーボールやバスケットなどで起こりやすいといわれています。
ランナー膝
膝の曲げ伸ばしを繰り返すことによって、膝の外側に痛みが現れるケガを「ランナー膝」といいます。ランナーに起こりやすいことから名付けられ、初心者ランナーや長距離ランナーが発症しやすいです。
タナ障害
タナ障害も膝の曲げ伸ばしを繰り返すことによって起こるケガです。膝のお皿付近にある「滑膜ヒダ」に炎症が起こり、痛みが生じたり膝が腫れたりします。
整骨院でできるスポーツ障害の治療法

スポーツ障害は、後遺症を残さないためにも整骨院などの専門家による治療が必要です。整骨院では、次のような施術を行います。
RICE療法
整骨院では、スポーツ障害の応急処置として「RICE療法」を用いることが多いです。RICE療法は、英語で次のような意味があります。
・「Rest」=安静
・「Ice」=冷却
・「Compression」=圧迫
・「Elevation」=挙上
RICE療法は症状の悪化を防ぐための応急処置であり、炎症の拡大を防止する役割があります。受傷直後にRICE療法を行うことで、ケガの早期改善にもつながると考えられています。
整復法
整復法は、骨や関節を正しい位置に戻す施術を指します。ケガの状態をしっかりと把握し、揉む、引っ張る、伸ばすなどの方法で改善を図ります。
固定法
包帯やテーピング、サポーターなどを用いて患部を固定する施術を固定法といいます。固定法を用いて患部を一定期間固定することで、可動を制限して早期回復につなげるのです。
手技療法
手技療法は、柔道整復師による手技を用いたマッサージのことです。揉んだり刺激を与えたりすることで自然治癒力を高める施術になります。
物理療法
物理的なエネルギーによって、身体に刺激を与えることで回復を図る施術を物理療法といいます。具体的な療法として、電気療法、光線療法、温熱療法、寒冷療法などがあります。
電気治療については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:整骨院の電気治療とはどんなもの?種類や効果について解説
運動療法
運動療法は、患部を動かすことで低下した運動機能を回復に導く施術のことです。運動療法によって骨格や筋肉を整えることで、痛みを和らげる効果が期待できます。
ただし、長期間の固定で患部が固まっている場合は慎重な施術が必要なため、経験豊富で頼れる施術者が在籍している整骨院を選ぶことが重要です。
くまのみ整骨院では、10年以上の経験を持つベテラン施術者やトップアスリートの施術経験があるスタッフが在籍しています。丁寧にカウンセリングを行い、お客様の身体の状態をチェックしてから、状態に合わせた施術をご提案しますのでお気軽にご相談ください。
まとめ
スポーツ障害は、日常的にスポーツをしている方に起こりやすいケガです。対処法を誤ってしまうと、症状が長引いたり後遺症を負ってしまったりする可能性もあります。早期回復を目指すためにも、スポーツでケガを負ってしまったら整骨院でしっかりと施術を受けるようにしましょう。
おすすめ記事
東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所
- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目4−5
新宿ウエストスクエアビル 6階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院プロデュース
プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所
- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階
- 営業時間
-
平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00
日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 成増駅前院
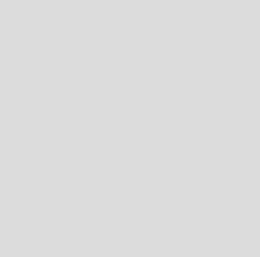
- 住所
- 〒175-0094
東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階
- 営業時間
-
平日・土日・祝:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所
- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:30/16:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所
- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00
くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階
- 営業時間
-
全日:10:00-20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所
- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 営業時間
-
平日:10:00~14:00/16:00~20:00
土曜:9:00~14:00/16:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所
- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00
くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所
- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~13:30/15:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所
- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所
- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 営業時間
-
平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30
日曜:8:30~12:30
祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |
| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |
▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所
- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所
- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所
- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 上尾院

- 住所
- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所
- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所
- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所
- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所
- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所
- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~14:00/16:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所
- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:30/14:30~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 草加院

- 住所
- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所
- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
コーポレートサイト
各院へのアクセス
東京都
埼玉県
- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階
- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階
- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階
- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28
- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階
- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階
- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階
- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階
- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階
- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階
- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階
- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階
- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階
- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階
- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階