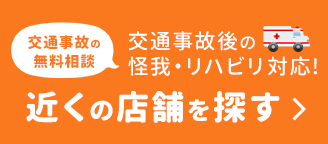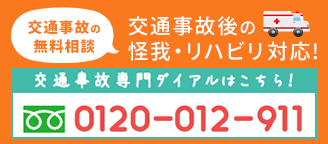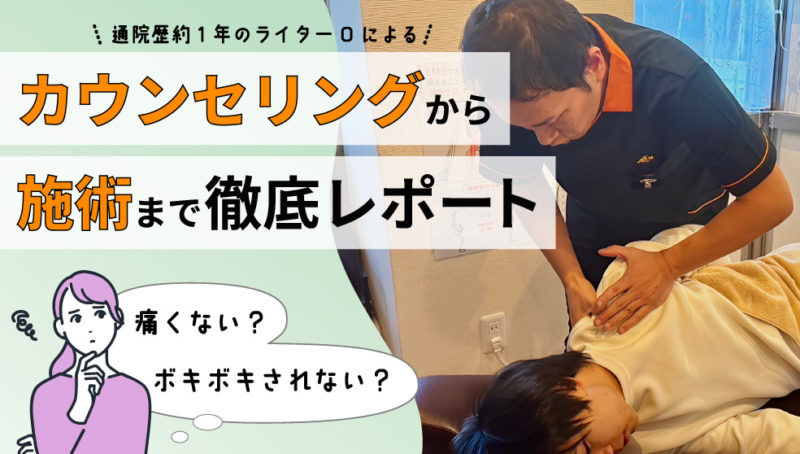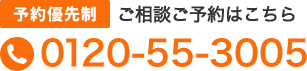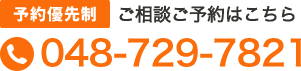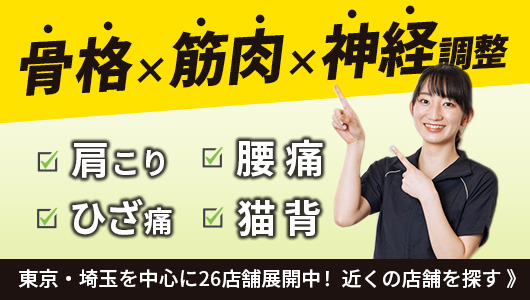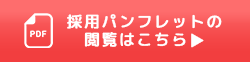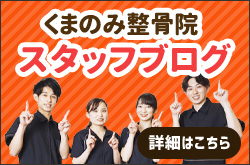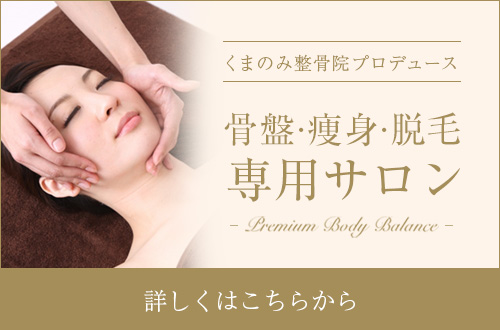冷え性や体の冷えから起こる頭痛と原因┃痛みを和らげる対策方法

冬の寒い時期に起こる頭痛は、体の冷えが原因となっている可能性があります。冷えが原因となっている頭痛は、対策をとることで緩和される場合があります。
本記事では、冷えによって起こる頭痛の種類や改善方法について解説しています。寒い時期の頭痛に悩んでいる人は参考にしてください。
冷え性や体の冷えから起こる頭痛

冷え性には、冷える場所によって異なるタイプが4つあります。また、冷えが原因で起こる頭痛には、2つの種類があります。
ここでは、冷え性のタイプと冷えから起こる頭痛について紹介します。
冷え性とは
冷え性とは、手足や体の全体が冷えることによって生じる体の不調や辛い症状のことを指します。しかし、冷え性は医学的な病名ではないため、体温や症状による明確な判断基準はありません。
一般的に冷え性の人は、季節を問わず暑い時期やまわりの人が寒さを感じていない状況でも、「体の冷えを感じている」とされています。
冷え性には、以下のように冷える場所によって異なる「4つのタイプ」があります。
・全身型
全身型の冷え性は、体全体が冷えるため体温が常に低い状態です。体質やストレス、生活習慣などによる極端な体力の低下が原因で起こります。
・内臓型
内臓型の冷え性は、体の表面が温かく内部が冷える状態です。自律神経の乱れにより体の表面から放熱が続き、体の内部の体温が下がることが原因で起こります。
・下半身型
下半身型の冷え性は、腰から下の部分が冷える状態です。お尻やふくらはぎの筋肉のこりによる血行不良が原因で起こります。
・四肢末端型
四肢末端型の冷え性は、手先や足先が氷のように冷える状態です。食事量が少ないことや運動不足が続いていることなどにより体内の熱量が不足することが原因で起こります。
冷え性が原因で頭痛が起きやすい人は、自分がどのタイプなのか知ることで、冷えと痛みを緩和するための対策が行えるでしょう。
冷えが原因の頭痛は「緊張性頭痛」と「片頭痛」
冷えが原因で起こる頭痛には、「緊張性頭痛」と「片頭痛」の2種類があります。
・緊張性頭痛
緊張性頭痛とは、首や肩周りの冷えによって血行が悪くなることで生じる頭痛です。寒い時期に首周りが冷える状態で長時間同じ姿勢でいると、首や肩周りの筋肉が硬くなります。首や肩のこりが、首や頭の神経を緊張させることで緊張性頭痛を引き起こします。
緊張性頭痛は、締め付けられるような痛みとともに首や肩のこりを感じるのが特徴で、ひどい場合は吐き気をもよおすこともあります。
・片頭痛
片頭痛は、ホルモンバランスの乱れやストレスが原因で起きる頭痛です。冷え性で常に体が冷えていると、寒さがストレスとなり、片頭痛を引き起こしやすくなります。
片頭痛は、左右のどちらかの頭が脈打つようにズキズキと痛むのが特徴です。痛みは、数分から数時間続くこともあります。
【頭痛】寒い環境や冷たい食べ物が原因で起こることも

頭痛は体の冷えだけではなく、外部環境や食べ物によって起こることもあります。
外部環境の変化を受けて頭痛が起こる
暑い場所から寒い場所へ移動すると、血管が収縮して頭痛が起こることがあります。外部環境が急激に寒くなると、血管が収縮して血行不良の状態になります。すると、首や肩周りの筋肉が緊張して、緊張型頭痛を引き起こします。
対して、寒い場所から暑い場所へ移動した場合も頭痛が起きることがあります。暑い場所への移動で起こる頭痛は、血管が急に拡張することで起きる片頭痛です。
冷たい食べ物や冷気による影響で頭痛が起こる
冷たい食べ物を食べることや冷たい空気を吸い込むことによる寒冷刺激によって頭痛が起こることがあります。寒冷刺激による頭痛は、以前は「アイスクリーム頭痛」と呼ばれていました。冷たいものを急いで食べると、頭がキーンと痛む症状で、多くの人が一度は経験したことがある現象です。
冷たい食べ物や空気による寒冷刺激は、顔や鼻、口の感覚を司る三叉神経に伝わり、脳が刺激を痛みとして感じることで頭痛を起こすと考えられています。
冷え性からくる頭痛を和らげる対策方法

冷え性からくる頭痛を和らげるには、今日から試せる方法と日常生活の習慣にしたい方法の2種類があります。
今日から試せること
冷え性は、日常生活の習慣が大きく関係しています。そのため、冷え性からくる頭痛は、食生活や睡眠などを見直すことで改善する可能性があります。
日頃の食生活を見直す
日頃の食生活では、根菜や発酵食品、生姜など体を温める効果がある食材を積極的に摂ります。食生活を見直し、体を温めることを心がけると、血行が促進されて肩こりが緩和されるため、とくに緊張型頭痛には効果的です。
質の良い睡眠をとる
質の良い睡眠をとることで、自律神経のバランスが整います。自律神経のバランスが整うと血管の働きが正常になり、体表面から放熱される内臓型冷え性が起こりにくくなります。また、自律神経の乱れは片頭痛の原因とされているので、睡眠によって自律神経が整うことは片頭痛の予防にもなります。
体を十分に温める
冷え性では、体を十分に温めることが大切です。外出する時は、ストールやマフラー、厚手の靴下を活用して体を冷気から守ります。また、入浴の際は、湯船に浸かることで冷えた体を温めて血行を促進させます。さらに、湯船に浸かることで、筋肉の緊張をほぐしリラックスさせる効果もあります。
習慣として取り入れると良いこと
普段の生活に、運動やマッサージを取り入れて習慣化させることで、冷え性を改善させる働きをします。
定期的に運動をする
体内に、適度な熱を保つには筋力が必要になるため、普段から定期的な運動をすることを心がけます。20分程度のウォーキングやランニング、すきま時間を使ってのスクワットなどをすると筋力が維持できます。
マッサージやストレッチを行う
デスクワークなどで長時間同じ姿勢でいる場合は、数分おきに体を動かすために肩や肩甲骨を中心に体を動かすストレッチを行います。また、マッサージで、硬くなった筋肉をほぐすことも効果的です。
症状に合った漢方薬を試してみる
冷え性からくる頭痛には、漢方薬を用いるのも有効です。漢方薬を選ぶ際は、症状に合ったものを選ぶ必要があるため、自己判断せずに、専門家に相談してみましょう。
まとめ
冷え性は、季節を問わず寒さを感じる状態のことで、緊張型頭痛や片頭痛の原因になることがあります。また、寒い時期の頭痛は外部環境の温度差や冷たい食べ物でも起こります。
冷えによる頭痛は、睡眠や食生活などの日常生活を見直し、運動やストレッチなどの習慣を取り入れることで改善する可能性があります。
頭痛の対策を行っても症状が改善しない場合は、くまのみ整骨院に相談してみましょう。
くまのみ整骨院では、症状に合わせた施術によって根本的な原因にしっかりとアプローチします。また、生活習慣が今の体をつくっているという考えから、本人が自分自身で体を管理できるよう指導を行っています。
冷えによる頭痛に悩んでいる人は、専門家に相談してみましょう。
東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所
- 〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目4−5
新宿ウエストスクエアビル 6階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:00/16:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院プロデュース
プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所
- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階
- 営業時間
-
平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00
日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |
※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 成増駅前院
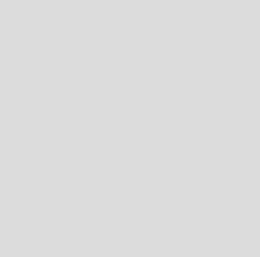
- 住所
- 〒175-0094
東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階
- 営業時間
-
平日・土日・祝:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院プロデュース
Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所
- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階
- 営業時間
-
平日:11:00~14:30/16:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所
- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00
くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階
- 営業時間
-
全日:10:00-20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所
- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 営業時間
-
平日:10:00~14:00/16:00~20:00
土曜:9:00~14:00/16:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所
- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 営業時間
-
平日:10:00~20:00
土曜:9:00~19:00
日曜・祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00
くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所
- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階
- 営業時間
-
平日:11:00~13:30/15:30~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所
- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所
- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 営業時間
-
平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30
日曜:8:30~12:30
祝日:9:00~18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |
| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |
▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所
- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所
- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所
- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 上尾院

- 住所
- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所
- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所
- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所
- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階
- 営業時間
-
全日:10:00~13:00/15:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所
- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階
- 営業時間
-
全日:10:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~21:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所
- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階
- 営業時間
-
全日:10:00~14:00/16:00~20:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所
- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:30/14:30~20:00
土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00
くまのみ整骨院 草加院

- 住所
- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所
- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F
- 営業時間
-
平日:10:00~13:00/15:00~20:00
土曜:9:00~13:00/15:00~19:00
日曜・祝日:9:00-18:00
定休日:火曜
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00
コーポレートサイト
各院へのアクセス
東京都
埼玉県
- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階
- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店
- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階
- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6
- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階
- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階
- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615
- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1
- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4
- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52
- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階
- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28
- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階
- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階
- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階
- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階
- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階
- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階
- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階
- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階
- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階
- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階
- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階